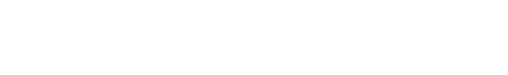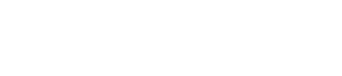身内のどなたか(「被相続人」といいます。)が亡くなられ、遺言がない場合は、民法の定めによって遺産分割協議を行います。その過程で弁護士がご相談にのり、円滑な遺産分割協議のためのアドバイスをしたり、必要な手続きの代理人をお引き受けすることができます。
遺産分割協議は、相続開始(被相続人が亡くなられた時)から何年以内にしなければならないという制限はありません。ただ、相続税の申告期限が「10か月以内」となっており、期限内に申告すれば税制上有利な点もあります。それまでに遺産分割協議を終えたいですが、できない場合は仮の相続税申告をすませて、引き続き協議を進めても良いのです。
ご相談は、それぞれのケースの成り行きによって、相続人全員の方々からお受けする場合もありますし、その中のお一人または数人の方からお受けする場合もあります。
相続人の間で分割協議がうまくできない場合には、調停や裁判の手続きをお引き受けします。これらの手続で複数の相続人の代理をお引き受けするのは、ご意見・ご希望に対立がない場合のみとなります。
※ 当事務所は、連携している複数の税理士がおります。相続はもとより、すべての事案について、どのような課税をされる可能性があるか、専門家の意見を聞いて事件処理を進めています。また、税務申告を依頼することもできます。
1.相続人の確定
法律が定める「法定相続人」を確定するには、被相続人が生まれた時までさかのぼって戸籍をとる必要があります。被相続人に配偶者・子ども・両親などがいなければ、兄弟姉妹やその子(甥や姪)が相続人となる場合もあります。関係者の本籍地が全国に広がっていたり、市町村合併で町名変更になっていたりするので、戸籍を取り寄せることはなかなか大変なことです。ご依頼があれば、戸籍を取り寄せ、法定相続人を確定するための調査をいたします。これにより、誰と誰の間で遺産分割協議をすればよいか、確定できることになります。
何らかの事情で、実子でない人が養子ではなく「実の子」として戸籍に入っている場合などには、まず、被相続人との間に親子関係が存在しないことを裁判で決めなければならないこともあります。
2.遺産の範囲の確定・・・遺産の調査
被相続人がのこした「遺産の内容」を明確に把握した上で、それぞれを誰が相続するか協議をすることになります。被相続人が、財産の正確な一覧表を作っていればよいのですが、そういうものがないこともあります。被相続人の生前に、誰かに財産を管理してもらっていた場合、相続人に対して財産管理の結果を報告してもらいますが、その内容に疑問が出てくることもないわけではありません。
そのような場合、弁護士が遺産調査をお引き受けして、法定相続人の代理人として、取引先やその可能性のある金融機関等を調査し、遺産の範囲を確定することができます。また、必要があれば、不当な支出がないかなど管理状況の分析もいたします。
遺産であるかどうか相続人間で意見が一致せず、裁判で決めてもらう必要がある場合もあります。
3.遺産分割協議書の作成
法定相続人と遺産の範囲が決まれば、分け方について協議をすることになります。協議は、相続人一同が集まってする場合もありますが、個別に連絡を取り合ったり、誰かが案を作って全員に送り、同意が得られて協議成立という場合もあります。
弁護士が、この分割案を作成したり、各相続人間の連絡・調整役を引受けることもありますし、特定の相続人の代理人として協議に参加することもできます。
「法定相続分」は、分割協議の一つの目安ですから、各人が受け取る財産が法定相続分より多くても少なくても、全員が納得すれば問題はありません。また被相続人の家業を共に担ってきた相続人が遺産形成に大きく貢献している場合や、被相続人の療養看護に、肉親として通常行う以上の特別な寄与をした場合など、法定相続分以上を相続することを法律上主張できる場合が例外的にあります。また,2019年7月施行の改正相続法では,法定相続人でなくとも,被相続人の介護などに特別な寄与をした第三者が法定相続人に対し相応の支払いをするよう請求できる仕組みが新設されました。このような主張ができるかどうかは、弁護士に相談されることをお勧めします。
協議がまとまったら、法定相続人全員で、「遺産分割協議書」を作成します。この書面で、不動産の登記手続や預貯金の払戻を受けられるような内容にしておく必要があります。弁護士は、この遺産分割協議書を作成することができます。
4.遺産分割調停・審判
法定相続人の間で分割協議がまとまらない場合は、家庭裁判所に調停の申し立てをすることになります。当事者全員が裁判所に出向いて、調停委員の仲介で話し合いを行います。不動産の評価に争いがあるような場合、不動産鑑定士の調停委員におよその評価をしてもらうことができ、納得性の高い解決を目指すことができます。
弁護士は、代理人としてこの調停をお引き受けします。申立の際裁判所に提出する資料は多岐にわたりますが、このような準備にも対応することができます。
調停でも協議ができず不成立になった場合は、家庭裁判所での「審判手続」に移行し、審理の上、裁判官が「審判」をします。これによって分割の仕方が決まることになります。現在では、預貯金も遺産に含まれ分割の対象となるという解釈がされているため、原則として遺産分割が終了するまで預貯金を引き出すことができなくなってしまいます。ただし、被相続人の残債務(入院費など)の支払いのため現金が必要になるような場合に備え,2019年7月施行の改正相続法では,一定の場合に預貯金の仮払いを認める制度が新設されました。
弁護士より
遺産分割協議の手続きは、複雑な要素があると、いくつもの法的手続きが必要になってしまうことがあります。「相続の開始」とは、親しいお身内を亡くされることですから、しばらくは相続問題など考える心の余裕をお持ちでない場合が多いでしょう。しかし、相続税支払いの対象となるかどうか(申告が必要か不要か)の見極めは早急に行う必要があります。加えて、分割協議がスムーズにいきそうか、難しくなる要因はないかという見極めも必要です。
一段落されたところで、まずは弁護士にご相談されることをお勧めします。ご自身で進められそうであればそのためのアドバイスをさしあげ、相談だけで終了する場合もあります。その後相続人の間で円満に協議ができ、遺産分割協議書の作成を依頼されることもあります。どうしても協議が円滑にいかない場合など、ケースに応じて適宜必要な対応をいたします。
弁護士費用
[法定相続人の調査]
手数料:3万円~(取り寄せる戸籍の数によります)
[遺産の範囲の調査]
手数料:10万円~(調査対象と内容によります)
[遺産分割協議書の作成]
手数料:10万円~(内容の複雑さによります)
[調停事件の着手金・報酬]
相続できる遺産の評価額の3分の1を「経済的利益」として、一般民事事件の報酬基準に基づいて計算します。たとえば、相続できる見込みの遺産評価額が1000万円なら、その3分の1(333万円)を「経済的利益」として、着手金はその5%+9万円、報酬は得られた額が見込みのとおり1000万円なら、10%+18万円となります。